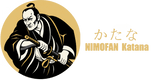| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 大きな沸(にえ)の結晶。 | Large nie crystals. |
| 刃文(はもん)から刃(は)に向かって走る細い線。 | Thin line that runs across the temper line (hamon) to the cutting edge (ha). |
| 規則正しい波状の表面模様(地肌)。 | Regular wavy surface grain pattern (jihada). |
| 幕末期(1853年〜1867年)に作られた刀。 | A sword made during an era in the late Edo period 1853-1867. |
| 日本の古代の国名で、現在の岡山県に該当します。 | Archaic province of Japan, modern-day Okayama prefecture. |
| 木刀のこと。別名「木剣」。 | See bokken. |
| 切先(きっさき)部分の刃文(はもん)。 | Temper line (hamon) of the blade point (kissaki). |
| 日本独自の測量単位。 | Japanese imperial form of measurement. |
| 地鉄に現れる黒く輝く沸(にえ)状の線。 | Black gleaming lines of nie that appear in the ji. |
| 明瞭に見える杢目肌(もくめはだ)。他の粗いパターンよりも鋼材がより澄んでいます。 | Distinctly visible mokume-hada with a clearer steel than in similar but coarser patterns. |
| 丁子油(ちょうじあぶら)、刃物の保存に使用されます。 | Clove oil, used for preserving blades. |
| 不規則な刃文(はもん)模様で、丁子のような形をしており、上部が丸く、下部が狭くなっています。 | An irregular hamon pattern resembling cloves, with a round upper part and a narrow constricted lower part. |
| 主に古来の時代に製造された直刀。 | A straight sword primarily produced during the ancient period. |
| 異なる長さの日本刀2振り(大刀と小刀)をセットで携帯する形式。 | In context any pair of Japanese swords of differing lengths (daito and shoto) worn together. |
| 柄や鞘に付いている筒状の金具。 | Tubular fittings on the tsuka or saya. |
| 日本の大刀、または大小(だいしょう)ペアの中で長い方の刀。 | Any type of Japanese long sword, the larger in a pair of daisho. |
| 柄(つか)の根元に装着される装飾的な補強カラー。 | Decorative reinforcing collar attached to the base of the tsuka. |
| 切先(きっさき)部分の刃(は)。 | The cutting edge (ha) of the blade point (kissaki). |
| 刀身の基部(まち)から切先(きっさき)に向かって細くなるテーパー。 | Tapering of the blade from the base (machi) to the point (kissaki). |
| 綾杉肌(あやすぎはだ)とも呼ばれます。 | See ayasugi-hada. |
| 1876年以降に作られた刀。 | Swords produced after 1876. |
| 後鳥羽上皇によって宮中に招かれた刀鍛冶たちで、月ごとに交代制で働きました。 | Swordsmiths summoned by the retired Emperor Go-Toba to work at his palace in monthly rotations. |
| ha | 刀身の焼き入れされた刃。 |
| 鎺(はばき)。鍔(つば)との間を緩衝し、刀身を鞘に固定する小さな金属輪。 | Small metal collar that buffers the tsuba and secures the blade into the saya. |
| 鎺元 | 鎬(しのぎ)の下にある刀身の部分。 |
| いちまいぼし | 沸文(はもん)が頂点に到達する前に戻るため、完全に焼き入れされた切先部分(きっさき)。 |
| いちもんじかえり | 短い返り(かえり)を伴って水平に直線的に戻る帽子(ぼし)。 |
| いくびきっさき | 短くて頑丈な切先(きっさき)。 |
| じ | 鎬(しのぎ)と沸文(はもん)の間の領域。 |
| じがね | 一般的に刀身の素材を指すために使用されます。 |
| じはだ | 製造過程で叩きと折り畳みによって生じた鋼材の表面模様。 |
| かえり | 帽子(ぼし)の先端から背(むね)へ延びる沸文(はもん)の一部。 |
| かいけん | 衣服に隠された短剣。 |
| かさね | 背(むね)全体で測定される刀身の厚さ。 |
| まち | 刀身本体と茎(なかご)を分ける切り欠き。 |
| まさめはだ | 直線的な表面肌模様(地肌)。 |
| まつかわはだ | 松樹の皮に似た表面肌模様(地肌)。 |
| ながかたな | 短刀(たんとう)よりも長い刃を持つあらゆる剣。 |
| ながまき | 通常は刀(かたな)サイズの刀身と、ほぼ同じ長さの非常に長い柄を持つ大型剣。 |
| なぎなた | 大きな弧を描く動きで扱われる長柄武器。 |
| さげお | 帯の中で刀を固定するために栗形(くりかた)に取り付けられる紐。 |
| さきはば | 横手(よこて)における刀身幅(みはば)。 |
| さきかさね | 横手(よこて)における刀身厚(かさね)。 |
| 太刀 | 60cm以上の刀身長を持つ湾刀。 |
| たまはがね | 日本刀の製造に使用される日本鋼。 |
| つか | 日本刀の柄。 |
| うちがたな | 帯の中で刃を上にして携行される日本刀。 |
| わかざし | しばしば刀(かたな)とペアで携行される短剣(大小)。 |
| やきば | 沸文(はもん)によって形成された刃の硬化部分。 |
| やきだし | 硬化した刃(焼き刃)が始まる刀身の部分。 |
| やきだし | 硬化刃(焼刃)が始まる鎺元のノッチ。 |
| 槍 | 日本の槍。 |
| 鑢目 | 茎に見られるファイルマーク。 |
| 横手 | 切先(きっさき)部分を刀身の他の部分から分ける線。 |
| 三昧 | たたらの異なる層からの玉鋼を混ぜ合わせる鍛造技法。 |